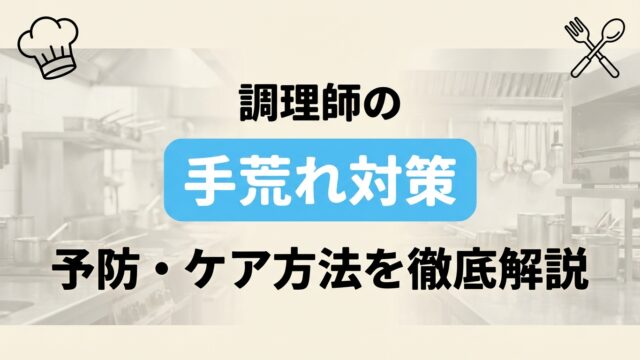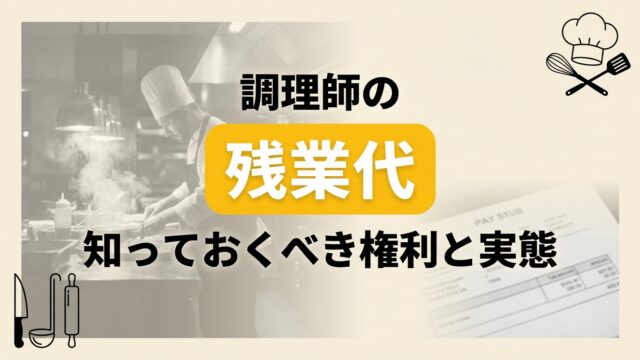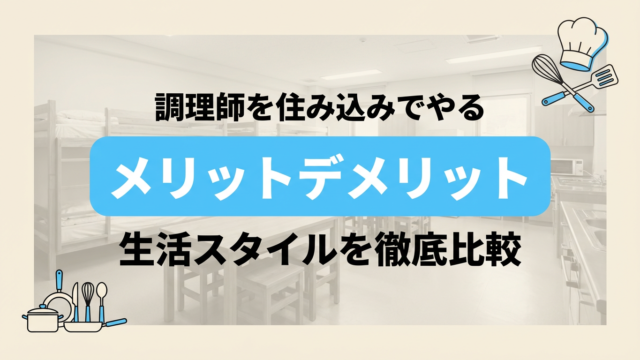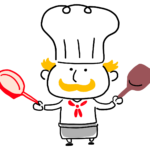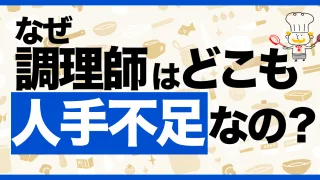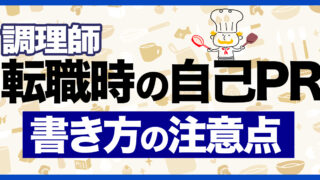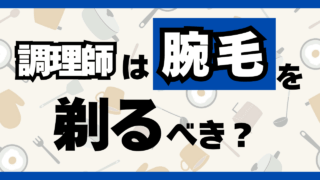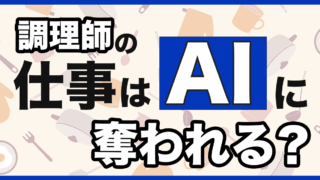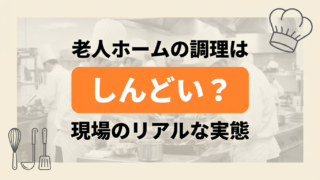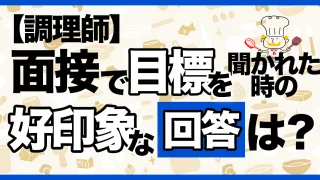※この記事はプロモーションを含みます
1. はじめに
調理師の仕事は、長時間労働・低賃金・体力的・精神的な負担が大きい職業のひとつです。厳しい環境の中で頑張っているにもかかわらず、上司や同僚から「お前は仕事ができないな」「使えない」などと言われると、大きなショックを受けることでしょう。
しかし、そう言われてしまった原因を見直し、適切な対処をすることで、仕事の進め方がスムーズになり、職場での評価も向上します。調理の現場はスピード・正確性・チームワークが求められるため、少しの工夫や意識の変化で状況を改善することができます。
本記事では、「仕事ができない」と言われたときに実践すべき5つのポイントを解説します。職場での立ち回りや作業の効率化を意識することで、調理のスキル向上だけでなく、職場での人間関係も良好にすることが可能です。
「自分は本当に仕事ができないのか?」と落ち込む前に、できることから改善を始めてみましょう。
2. 仕事の段取りを組み立てる
調理の現場では、段取りの良し悪しが仕事の効率を大きく左右します。仕事ができないと言われてしまう人の多くは、作業の優先順位を考えず、目の前の仕事をただこなすことに精一杯になってしまっていることが多いです。
1日の流れを把握し、優先順位を決める
まずは、その日にやるべき作業を明確にし、優先順位を決めることが大切です。たとえば、朝出勤したら、以下のような手順で仕事の流れを整理しましょう。
- 今日の業務をリストアップする
- 仕込み、調理、清掃など、すべての作業を洗い出す。
- 優先順位を決める
- 時間がかかる作業、すぐに取りかかるべき作業を整理する。
- 火を使う作業(焼く・煮るなど)は、時間を要するため早めに取りかかる。
- 冷蔵・冷凍食材の解凍や漬け込み作業など、時間のかかる準備は先に行う。
- 作業をまとめて効率化する
- 同じ道具や材料を使う作業を一緒に進めることで、無駄な動きを減らす。
作業をまとめて時短するコツ
仕事の段取りを考える際に、「一緒にできることはまとめる」という視点を持つことが重要です。
例えば、きんぴらごぼうを作る際に醤油を計量する場合、その醤油を他の煮物用の分もまとめて計量することで、作業の手間を省くことができます。
これにより、
- 調味料の出し入れの回数を減らせる
- 計量カップを洗う回数を減らせる
- 無駄な移動を減らして作業効率を上げる
このような小さな工夫を積み重ねることで、全体の作業スピードが向上し、「段取りが良い」と評価されるようになります。
段取り上手になるための意識改革
- 「次に何をするべきか?」を常に考える
- 仕事の流れを予測し、先手を打つ
- 無駄な動きを減らし、効率的に動く習慣をつける
仕事ができる人ほど、「この作業をしながら、次に何をすべきか」を考えながら動いているものです。上司から「仕事ができない」と言われる人ほど、目の前の作業に集中しすぎて全体の流れを見れていないことが多いので、意識的に改善していきましょう。
3. めんどくさい作業を効率化する工夫
調理の仕事には、「地味だけど避けられない作業」が多く存在します。例えば、食材の下処理、洗い物、清掃、仕込み作業などです。これらを後回しにしたり、嫌々やっていると、時間の無駄やストレスの原因になり、結果として仕事の効率が悪くなってしまいます。
「めんどくさい作業」を効率化するために、少しの工夫を取り入れてみましょう。
洗い物を効率化するコツ
調理の現場で避けて通れない作業のひとつが「洗い物」です。特に忙しい時間帯に洗い物が溜まると、作業スペースが狭くなり、スムーズに調理ができなくなります。
そこで、洗い物を効率的に進めるためのコツを紹介します。
✅ 大きなものから先に洗う
- 鍋やフライパンなどの大きな調理器具は、最初に洗う。これにより、作業スペースを確保でき、小さいものをスムーズに洗える。大きいものを後回しにすると、シンクが埋まってしまい、作業効率が下がる
✅ 調理中の合間にできる範囲で洗う
- 食材を煮ている間や焼いている間に、使い終わった道具をサッと洗っておく。手が空いたときに少しでも片付けるという意識を持つと、後の負担が減る
✅ 洗剤やスポンジを適切に使う
- こびりついた汚れは、お湯につけてふやかしておく
- すぐに洗えない場合は、水を張っておくだけでも汚れが落ちやすくなる
- 油物は洗剤を入れた水につけておく
こうしたちょっとした工夫を取り入れるだけで、洗い物のストレスが軽減し、結果として仕事全体のスムーズさにもつながります。
仕込み作業を効率化するコツ
仕込み作業も調理の現場では欠かせませんが、時間がかかる作業のひとつです。以下のポイントを意識することで、作業効率を上げることができます。
①作業をグループ化する
同じ道具・材料を使う作業をまとめて行う。
例えばにんじんの千切り、キャベツの千切りなど、同じ包丁・まな板を使う作業はまとめる。
これによりいちいち道具を変える手間が省ける
- 可能なら、フードプロセッサーやピーラーなどの道具を活用する。
- 力を入れて切るより、効率的な道具を使うことで作業スピードがアップする
- 食材の保存方法を工夫することで、無駄な仕込み作業を減らす
- 例:カット野菜は水にさらしておくことで変色を防げる
- 事前に仕込めるものは仕込んでおくことで、当日の作業を減らせる
めんどくさい作業を効率化するメリット
こうした工夫を取り入れることで、単に作業が楽になるだけでなく、時間短縮・ストレス軽減・業務全体のスムーズ化といったメリットがあります。
めんどくさい作業を避けるのではなく、「どうすれば楽にできるか?」を考える習慣をつけることが大切です。これを意識するだけでも、仕事の進め方が大きく変わり、結果的に「仕事ができる人」に近づくことができます。
4. 上司を観察し、学ぶ
調理の現場では、上司の動きを観察し、仕事のやり方を学ぶことがとても重要です。多くの上司は、経験を積んで効率よく仕事を進める術を身につけています。そのテクニックを盗み、自分の仕事に活かせるようになれば、成長スピードも格段に上がります。
また、上司の性格や考え方を知ることも、円滑な職場関係を築く上で欠かせません。 仕事ができるようになるだけでなく、職場での居心地も良くなります。
上司の仕事のやり方を観察し、真似する
仕事のスピードや段取りが上手な上司を見ていると、無駄のない動きをしていることがわかります。その動きを観察し、「なぜこのタイミングでこの作業をしているのか?」 を考えながら仕事をしましょう。
✅ 上司の段取りを学ぶ
- どの作業をどの順番でこなしているのか
- どのタイミングで何を準備しているのか
- 仕込みから調理、本番の流れまで、一貫して動きを観察する
✅ 上司がよく使うテクニックを盗む
- 包丁の使い方、火加減の調整方法、味付けのタイミングなど
- 効率的な動きや、細かい調理技術を意識して取り入れる
こうした点を意識することで、自分の仕事の進め方がスムーズになり、評価も上がるはずです。
上司の性格を把握し、コミュニケーションを円滑にする
仕事のやり方だけでなく、上司の性格や価値観を理解することも大切です。良好な人間関係を築くことで、仕事がやりやすくなり、教えてもらえる機会も増えます。
✅ 上司の好みや性格を観察する
- どんなことにこだわっているのか?
- どんな話題に興味があるのか?
- 怒りやすいポイントはどこか?
✅ さりげない雑談を活用する
上司が忙しくないタイミングを見計らって、さりげなく雑談をしてみましょう。例えば、「〇〇さんってお酒好きでしたよね?この間こんなお店を見つけたんですが、行ったことありますか?」 など、仕事以外の話題を振ることで、距離が縮まりやすくなります。
雑談が好きではない上司もいるので一度話しかけてみて見極めましょう
✅ 上司と関係が良好だと仕事がしやすくなる
上司との関係が良くなると、
- 仕事の相談がしやすくなる
- 指示が的確にもらえるようになる
- 評価が上がり、仕事を任せてもらいやすくなる
結果的に、仕事のスキルも向上し、職場でのストレスも軽減されるはずです。
上司との関係を良くするための意識
- 「この人から学ぼう」という姿勢を持つ
- 指示を受けるだけでなく、積極的に観察する
- 雑談を通じて、適度な距離感を保つ
「仕事ができない」と言われているうちは、上司から厳しい指摘を受けることもあるかもしれません。しかし、上司の仕事ぶりをよく観察し、学ぶ意識を持つことで、少しずつ成長していくことができます。
5. チームワークを意識し、周りの動きを読む
調理の現場は、個人プレーではなくチームワークが重要です。厨房内のスタッフ同士はもちろん、ホールスタッフとの連携も欠かせません。仕事ができないと言われる人の多くは、「自分の作業に集中しすぎて、周りを見ていない」 という共通点があります。
周囲の動きをよく観察しながら行動することで、スムーズな連携が取れるようになり、結果的に「仕事ができる人」と評価されるようになります。
周りの動きを見る習慣をつける
厨房では、他の人が何をしているのかを常にチェックすることが重要です。自分の作業だけに集中していると、連携が取れず、仕事が遅れたりミスにつながったりします。
- 上司が肉を焼いているなら、その料理のソースやお皿の準備をする
- 隣の人が盛り付けをしているなら、食材や器具をすぐ取れる位置に置く
- ホールスタッフが料理を運んでいるなら、新しいオーダーが来るタイミングを予測する
- 今日の営業で仕込んでいたものがなくなったらメモをしておいて、上司に言われる前に仕込みを終えておく
一歩先を読んだ行動を意識する
仕事ができる人ほど、「次に何が必要か?」「次は何をやるべきか」を考えながら動いています。 これができるようになると、上司や同僚から「助かるな」「気が利くな」と評価されるようになります。
例えば、
- 仕込みの段階で、次の工程を見据えて準備をしておく
- 皿洗いのときも、次に使う道具を考えながら片付ける
- キッチンの動線を考え、邪魔にならない位置で作業する
ホールスタッフとの連携も大切
厨房の中だけでなく、ホールスタッフとの連携も仕事のスムーズさに影響します。ホールの動きを把握し、オーダーの流れを意識することも大事なポイントです。
- ホールスタッフの動きを見て、料理の提供タイミングを調整する
- 忙しい時間帯は、ホールとのやり取りをスムーズにする
- 食器の返却が増えてきたら、洗い場の負担を予測して動く
こうした視点を持つことで、厨房とホールの連携がうまくいき、全体の業務効率がアップします。
周りをよく見て動ける人は評価される
- 自分の仕事だけでなく、チーム全体の流れを意識する
- 一歩先を読んだ行動ができるようになる
- 周囲とのコミュニケーションを大切にする
仕事のスキルだけでなく、周りの動きを見て気配りができる人は、職場で重宝される存在になります。 ぜひ意識してみましょう。
6. 技術面での遅れは焦らずコツコツと
調理の仕事では、包丁さばきや火加減の調整、盛り付けのセンスなど、さまざまな技術が求められます。しかし、これらのスキルは一朝一夕で身につくものではありません。
仕事ができないと言われる人の中には、技術の未熟さを理由に怒られてしまう人も多い でしょう。しかし、技術は時間をかけて身につけていくものです。焦ることなく、コツコツと練習を重ねることが大切です。
技術の向上には時間がかかると理解する
包丁さばきや調理のスピードは、経験を積むことで自然と上達します。最初から完璧にできる人はいません。
例えば、包丁の技術に関しても、
- 最初は千切りがうまくできなくても、何度も切るうちに均一に切れるようになる
- 皮むきが遅くても、繰り返すうちにスムーズにできるようになる
- 素早く正確に切るには、手の動きを体に覚えさせることが重要
上司に「野菜の切り方が遅い」「盛り付けが下手」と怒られても、気にしすぎないことが大切です。 大事なのは、「できないから諦める」のではなく、少しずつでも上達する努力をすることです。
コツコツと練習を積み重ねることが大切
技術を向上させるためには、日々の仕事の中で少しずつ改善していくことが大事です。
✅ 練習を継続するためのポイント
- 焦らず、できることから確実にこなす
- 無理にスピードを上げようとすると、ミスが増えてしまう
- 正確にこなすことを優先し、徐々にスピードを上げる意識を持つ
- 上手な人のやり方を観察する
- 包丁さばきが上手な人の手元を見て、動かし方を真似する
- 何を意識しているのか聞いてみるのも効果的
- オフの時間も活用する
- 家で包丁の練習をしたり、調理動画を見て学ぶ
- 自分で料理を作りながら、新しい技術を試してみる
技術習得のペースは人それぞれ
「同期のあいつはもうできるのに、自分はまだできない……」と焦ることもあるかもしれません。しかし、技術の習得スピードは人それぞれ違います。
むしろ、最初は不器用でも、「確実にやる」「丁寧に仕上げる」ことを意識している人の方が、結果的に良い仕事ができるようになることも多いです。
気持ちの持ち方も大事
- 失敗しても落ち込みすぎない
- できることを増やしていく意識を持つ
- 周囲と比べず、自分のペースで成長する
技術面での成長は一歩ずつですが、コツコツ努力を積み重ねていけば、必ず上達します。 大切なのは、「できない」と諦めず、前向きに取り組むことです。
7. それでも辛いときの選択肢
どれだけ努力をしても、職場の環境や人間関係が合わずに辛いと感じることもあります。 仕事を改善しようと頑張っても、職場の雰囲気や上司との相性が悪いと、どうしても辛さが残ることがあります。
そうした場合は、無理をせず、転職を視野に入れることもひとつの選択肢です。
職場が合わないことは珍しくない
調理業界は店舗や職場によって雰囲気が大きく異なります。
- 理不尽な怒られ方をする(指導ではなくパワハラ)
- 休みが極端に少なく、体調を崩してしまう
- 上司や同僚との人間関係がどうしても悪い
- 改善しようと努力しても、評価されない・報われない
このような状況では、いくら頑張ってもメンタルや体が持たなくなってしまうことがあります。「この職場にいる限り、成長できない」と感じるなら、無理に続ける必要はありません。
転職を考えるときのポイント
転職を考える際に大事なのは、「自分が本当に辛いのか? それとも単に甘えなのか?」を冷静に判断することです。
✅ 転職を考えた方がいい状況
- 精神的・肉体的に限界を感じている
- どれだけ努力しても、職場環境が改善しない
- 自分の成長が感じられず、将来が見えない
✅ まだ頑張れるかもしれない状況
- 上司の指摘が厳しいが、仕事のスキルアップにはつながっている
- 失敗が続いているが、自分の努力次第で改善できる可能性がある
- 職場の人間関係に問題はないが、単に仕事が難しいと感じる
転職を成功させるためのポイント
もし本当に限界を感じて転職を考えるなら、できるだけ次の職場選びを慎重に行うことが大切です。
- 飲食業界に強い転職エージェントを利用する
- 自分のやりたい業態(和食・洋食・ホテルなど)を明確にする
- 給与・労働環境・福利厚生をしっかり確認する
調理の仕事はどこでも同じではありません。働く環境によって、労働時間や人間関係、給料などが大きく変わるため、慎重に職場を選ぶことが重要です。
転職を考えるなら「フーズラボ」がおすすめ
もしあなたが転職を検討しているなら、飲食業界専門の転職エージェント「フーズラボ」を活用するのがおすすめです。
✅ フーズラボの特徴
- 飲食業界に特化した非公開求人が多数
- 希望条件に合った職場をプロが紹介
- 転職サポートが充実しており、面接対策や履歴書の添削もしてくれる
飲食業界の転職は情報収集が大切ですが、個人で探すのは限界があります。 フーズラボを利用すれば、一般には公開されていない「好条件の求人」を見つけることができます。
まずは、無料登録して自分に合った求人があるか確認してみましょう。
🔽 非公開求人多数!フーズラボの詳細はこちら 🔽
👉 フーズラボの公式サイトをチェック
「辞めるのは甘え?」と悩んでしまう人へ
「仕事ができないから逃げるのはダメなんじゃないか?」と悩む人もいるかもしれません。ですが、合わない環境で無理を続ける方が、長期的にはデメリットが大きいです。
- 過労で体調を崩す(睡眠不足・体力の消耗)
- メンタルが病んでしまう(うつ状態・モチベーション低下)
- 料理が嫌いになってしまう(本来のやりがいを失う)
もし、「もう本当に限界だ」と感じたら、無理をせず転職を考えましょう。
調理業界にはさまざまな職場がある
- レストランやホテルのキッチン(安定した環境が多い)
- 給食センターや社員食堂(比較的労働時間が規則的)
- 食品開発や料理教室の講師(調理経験を活かせる別の仕事)
視野を広げれば、あなたに合った職場がきっと見つかります。今の職場に固執せず、より良い環境を探すことも前向きな選択肢です。
🔽 まずは無料で求人をチェック! 🔽
👉 フーズラボの公式サイトを確認する
8. まとめ
調理の仕事は体力的・精神的に厳しい職業です。その中で、上司や同僚から「仕事ができない」と言われるのはとても辛いことですが、そこで落ち込んで終わるのではなく、何が原因なのかを冷静に分析し、改善していくことが大切です。
「仕事ができない」と言われたときに実践すべき5つのこと
✅ 1. 仕事の段取りを組み立てる
- 1日の流れを把握し、優先順位を決める
- 作業をまとめて効率化する
✅ 2. めんどくさい作業を効率化する
- 洗い物や仕込み作業を工夫し、無駄な時間を減らす
- 「どうすれば楽にできるか?」を考える習慣をつける
✅ 3. 上司を観察し、学ぶ
- 上司の仕事のやり方を観察し、効率的な動きを真似する
- 雑談を活用し、良好な関係を築くことで仕事を覚えやすくする
✅ 4. チームワークを意識し、周りの動きを読む
- 自分の仕事だけでなく、周囲の動きを意識して補助する
- 一歩先を読んだ行動を心がける
✅ 5. 技術面での遅れは焦らずコツコツと
- 包丁さばきや調理技術は、継続的な練習で上達する
- 他人と比べず、自分のペースで成長する
それでも辛い場合は、転職も視野に入れる
- どれだけ努力しても環境が合わないなら、無理に続ける必要はない
- 調理の仕事は職場によって大きく違うので、より良い環境を探すのも一つの手
- 飲食業界にはレストラン、ホテル、給食センター、食品開発など多様な選択肢がある
成長を続ければ、必ず「できる調理師」になれる
仕事ができないと言われたとしても、努力次第で成長し、職場での評価を変えることができます。 大切なのは、「仕事ができない」と落ち込むのではなく、「どうすればできるようになるか?」を考え、実践することです。
今はまだ未熟でも、コツコツと努力を続けることで、必ず成長できます。 今日からできることを一つずつ実践し、「仕事ができる調理師」への第一歩を踏み出しましょう。
おわりに
最後までお読みいただきありがとうございました。調理の仕事は厳しいですが、成長すればするほどやりがいのある職業です。今回紹介した方法を試しながら、自分に合った働き方を見つけていきましょう。